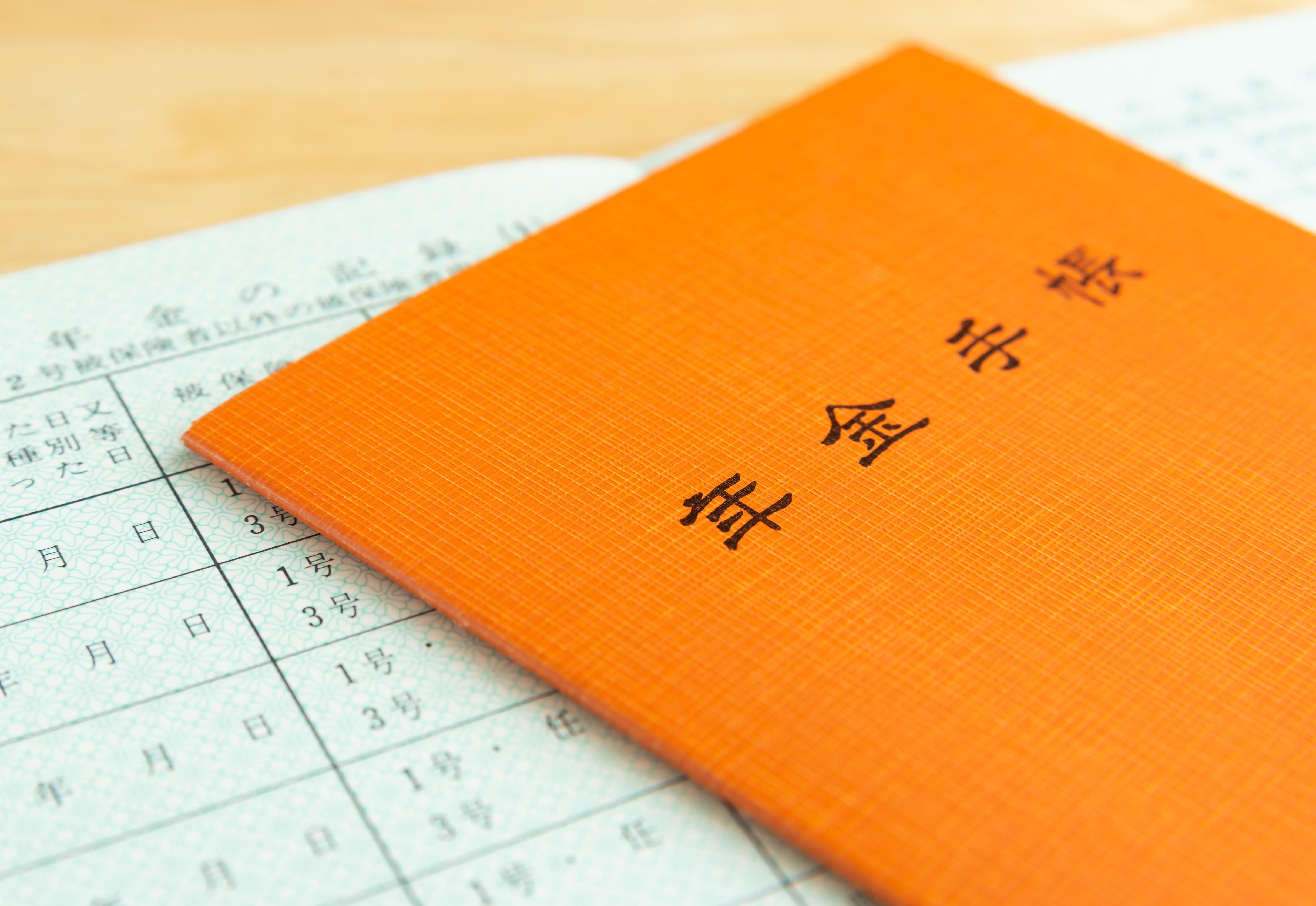住民税は、私たちの生活に欠かせない公共サービスの財源として重要な役割を果たしています。この住民税の納税は義務のため、必ず支払うものですが、節税することができれば、家計の節約になります。今回はその方法を解説していきます。
まずは住民税の基本をおさらい
会社員の場合、住民税は給与から引かれているのは理解しているけれど、どのように決まっているのかなど具体的な仕組みを理解していない人もいるでしょう。まずは基本を解説します。
①住民税の納付額
住民税は「均等割」と「所得割」の2つで構成されています。「均等割」は所得に関係なく一律の金額を負担する部分で、誰もが均等に5000円を負担します。一方、「所得割」は前年の所得に応じて課税される部分で、課税所得金額に対して一律10%の税率が適用されます。この2つを合計した金額が納税額になります。
②住民税の納付方法
会社員の場合、特別徴収として給与から天引きされ、毎年6月~翌年5月までの12回で分納していきます。一方、自営業者などの場合、普通徴収として自ら納付書等で納め、納期は6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回に分かれています。
住民税を安くする3つの方法をチェック
それでは、「住民税を安くする方法」を見ていきましょう。住民税は前年の所得に基づき算出されるため、課税所得を抑えることで税額を減らせます。収入自体を減らすことが難しくても、各種所得控除を活用すれば課税所得を抑えられます。主な方法としては、以下の3つがあります。
節税方法① 生命保険料控除を受ける
生命保険、医療保険、個人年金保険などに加入している場合、年間の支払保険料に応じて生命保険料控除を受けられます。生命保険料控除は、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類があり、住民税では各控除の限度額が2.8万円、合計で最大7万円の控除が可能です。会社員の場合は、年末調整で会社に申告することで、控除が受けられます。
節税方法②:医療費控除を受ける
年間の医療費が10万円を超えた場合(または、総所得金額が200万円未満の人はその5%を超えた場合)医療費控除を受けられます。対象になるのは、治療費・薬代だけでなく、通院時の交通費や入院中の食事代、鍼灸などの施術費用も含まれます。また、生計を一にする家族の医療費も合算可能。ただし、会社員でも確定申告が必要になります。
節税方法③:iDeCoに入る
iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入すると、拠出した掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となり、所得税や住民税の軽減になります。 例えば、毎月2万円(年間24万円)の掛金を拠出している会社員の場合、住民税は年間2万4000円軽減されます。会社員なら、iDeCoの控除も年末調整の申告でOKです。
上記の3つの方法は条件を満たせば誰でも利用できます。自分が受けられる控除を確認することをおすすめします。
なお、経済的に親の面倒を見ている人なら、親の所得が48万円以下(給与所得者は年収103万円以下)であれば、親を扶養に入れることで扶養控除を受けられます。住民税の扶養控除額は、親が70歳未満であれば33万円、70歳以上で同居している場合は45万円、別居している場合は38万円となっており、控除額分だけ住民税が軽減されます。
まとめ
住民税の負担を軽減するためには、生命保険料控除、医療費控除、iDeCoへの加入などの所得控除を活用することが有効です。自分が受けられる控除を理解して、取りこぼしのないようにきちんと申告しましょう。